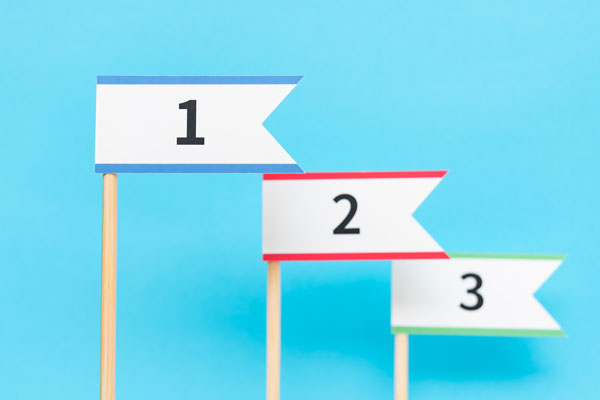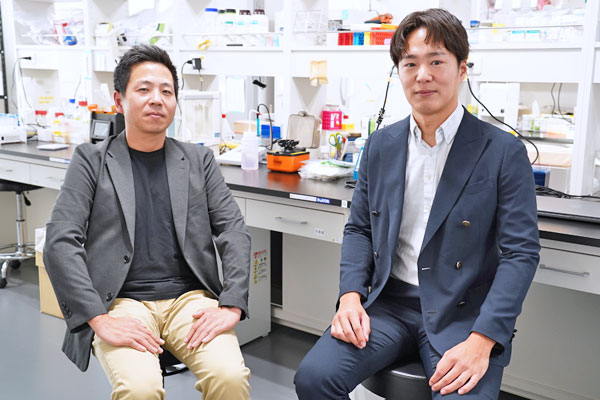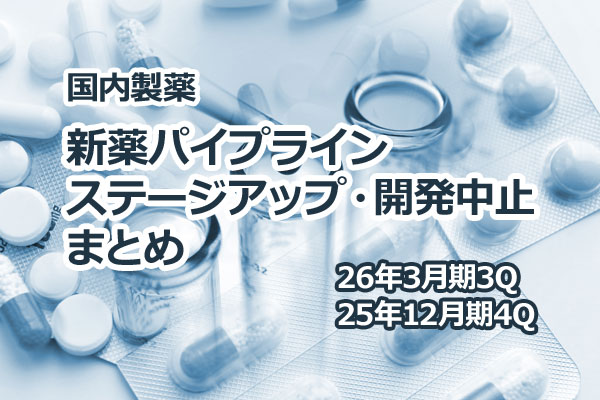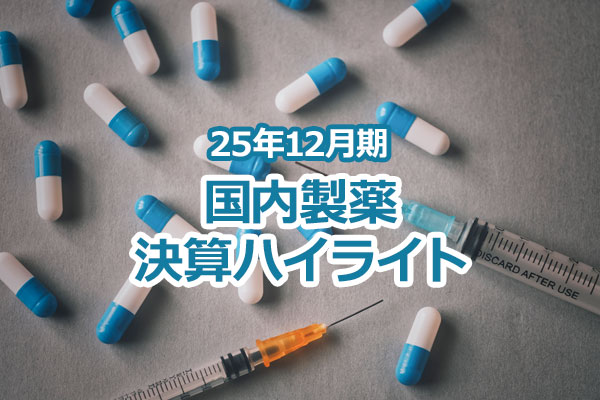今年に入り、クオリプスと住友ファーマがiPS細胞由来の再生医療等製品を相次いで承認申請し、iPS細胞の実用化に注目が高まっています。そうした中、「日本の再生医療は正念場にさしかかっている」と話すのは、慶應義塾大学再生医療リサーチセンターの岡野栄之センター長。自身も再生医療ベンチャーに関わり、実用化に向けた研究開発を進める同氏に話を聞きました。
脊髄損傷の再生医療、一定の有効性示唆
――CSO(最高科学責任者)を務めるケイファーマで実用化を目指すiPS細胞由来の亜急性期脊髄損傷治療について、3月に医師主導臨床研究の結果を公表しました。
われわれが開発しているのは、亜急性期脊髄完全損傷の患者にiPS細胞由来の神経前駆細胞を移植し、機能回復を目指す治療法です。予定していた全4例の経過観察を昨年11月に終え、目的としていた一定の安全性が確認できました。
有効性についても一定の示唆が得られました。今回の4例では、受傷後52週時点の運動機能(100点満点の指標)がベースラインから中央値で13点改善し、重症度が同程度の患者集団で過去に報告された平均的な改善(4~7点)を上回りました。4例中2例が完全麻痺から不完全損傷に回復し、うち1例は、腕を上げ、立ち上がって歩くところまで回復しました。残りの2例も回復は見られましたが、完全損傷を脱するには至っていません。
現在は、治療効果が著しい患者とそうでない患者の違いを分析し、論文化を進めている最中です。今後ケイファーマで行う企業治験では、この分析をもとに試験デザインを組んでいけるのではないかと期待しています。
――脊髄損傷に対する再生医療の研究には2000年代から取り組んでいます。
今回われわれが移植した細胞は、京都大iPS細胞研究所(CiRA)で作製されたiPS細胞を、大阪医療センターで移植用神経前駆細胞に分化させて製造しています。もともとはES細胞で開発した技術ですが、2007年にヒトiPS細胞が樹立されたのを機にiPS細胞で研究を進めてきました。
とはいえ、当初のiPS細胞はレトロウイルスを使って作製しており、がん化のリスクなど課題が山積みでした。11年にCiRAがエピソーマルベクターを使った作製方法を開発して前進したものの、移植細胞のソースとして利用できるようになるまで試行錯誤が続きました。われわれもそれに合わせて何度も研究を一からやり直し、いいものができたと思ったらまた振り出しに戻ったりと、実際に臨床に移るまでに何年も費やしました。症例数が年1例程度ということもあり、臨床研究にも4年かかりましたが、悪くない結果が得られたことに安堵もあります。
私自身は慢性期の脊髄損傷に対する別の治療法の開発にも取り組んでいます。軸索がある程度残っている慢性期不完全損傷の患者さんでは、著しい脱髄が起こることがある。そこに髄鞘形成能の高い細胞を移植する治療法を考えています。
スケーラビリティ、重要な課題
――もう1つ、創業科学者として関わるサンバイオでは製品の発売が見えてきています。iPS細胞ではありませんが、こちらも長い歩みとなりました。
本当にやっとここまで来たなと。01年に創業して四半世紀が経とうとしていますから。どちらの研究も、今になってみればなんでこんなに時間かかったんだろう、と思うことはあります。でも、その時はその時で一生懸命やっていたのは間違いありません。米カリフォルニアのガレージベンチャーのようにスタートし、途中、リーマンショックで潰れかけたこともありました。起死回生を果たしてバンデフィテムセルの脳梗塞の臨床試験を始めたのが2011年です。
しかし、脳梗塞では大規模治験がうまくいかず、外傷性脳損傷にターゲットを切り替えました。RCT試験で結果を出して申請しましたが、今度は製造安定性の問題に直面しました。条件付き承認制度の運用が始まったころに比べて厳しい条件だと感じた部分はありますが、やはりスケーラビリティを考えると非常に重要な要素ですし、今後は必須到達目標になってくるのだろうと思っています。そうなることで本承認の確度も高まり、制度としても国際的な信用度が高まるでしょう。
再生医療の将来を考えると、スケーラビリティは今後を左右する極めて重要な課題だとも考えています。日本はまだまだ培養を人の手作業で行っているところがあり、自動化技術やAI技術は未成熟です。海外を見ればわかるように、これからはAIも活用した自動培養技術が大きく発展していくと予想されます。
たとえば米国に拠点を持つセルリノ・バイオテックは、AIで細胞の形態を学習し、異常な細胞をレーザーで除去するクローズドな自動培養システムを開発しています。こうした新しい技術は、将来的に再生医療のコストダウン実現にもつながるでしょう。「いいものをより安く」の世界に近づいていくはずです。これまでの投資を無駄にしないためにも、日本のバイオベンチャーや製薬企業、CDMOもこのスピードに遅れずについていかなければならないと考えています。
iPS細胞の発見をきっかけに、日本は先陣を切って再生医療をやりやすい土壌を作ってきました。実用化にも世界から高い注目が集まっており、我が国は正念場を迎えていると思います。
臨床に役立たなければ本物じゃない
──基礎研究と社会実装の両方に挑み、さらにはLINK-Jの理事長を務めるなど産業振興にも積極的に関わっています。
20世紀の終わりごろは、まだまだ低分子全盛の時代でした。再生医療に興味を持つ企業はあっても、一緒に開発を進めてくれるところはなかなか現れない。「細胞は手に負えない」と。だから自分たちでやるしかなかったわけです。それは確かにここまでやってきたひとつの原動力だったと思います。
私自身はもともと基礎研究一本でした。転機となったのは、筑波大から大阪大に移籍した1997年。当時の医学部長にあいさつに行くと、「あんたの研究、臨床に役立たなかったら本物じゃない」と言われたんです。社会に還元できない、もっと俗っぽく言えば儲けにならないような研究で満足するなよ、と。
その翌年、「Musashi」(RNA結合タンパク質)を使ってヒトの脳に神経幹細胞があることを突き止めました。「脳も再生する」と話題になり、メディアに取り上げられると、患者さんから手紙をもらうようになり、「基礎研究の成果を臨床に還元する時期かな」と考えるようになりました。
実際にことが動き出したのは、01年に母校の慶應に戻ってからです。私の研究に関心を持ったサンバイオのファウンダーである森敬太氏と川西徹氏がやってきました。彼らと一緒にやる中で、私も基礎から実用化の橋渡しをするトランスレーショナルリサーチの面白さに気づいたんでしょうね。考えてみれば、祖父は天文学者で、父親は三井不動産に務める企業人でした。私の遺伝子には研究とビジネスの両方が刻まれているのかもしれませんね。
――今年7月には国際幹細胞学会(ISSCR)の理事長に就任しました。
ISSCRでは、南米やアフリカといった地域での再生医療の普及にも挑戦します。たとえばアフリカによく見られる鎌状赤血球症には根本治療として遺伝子治療が承認されていますが、価格が高い。アフリカの人々にも届く価格で提供できるよう、国際的な取り組みを推進していく必要があると考えています。スケーラビリティの課題解決との両輪で、もっと世界に再生医療を広めていきます。