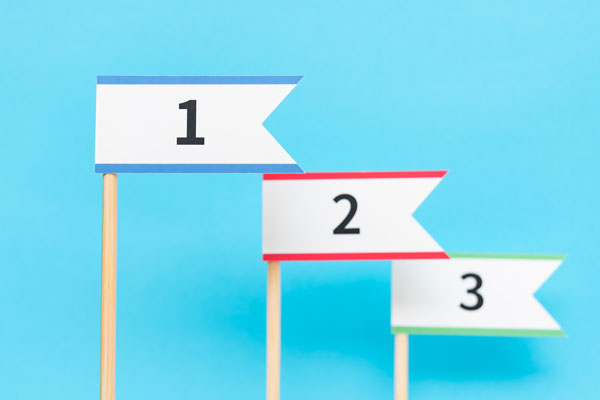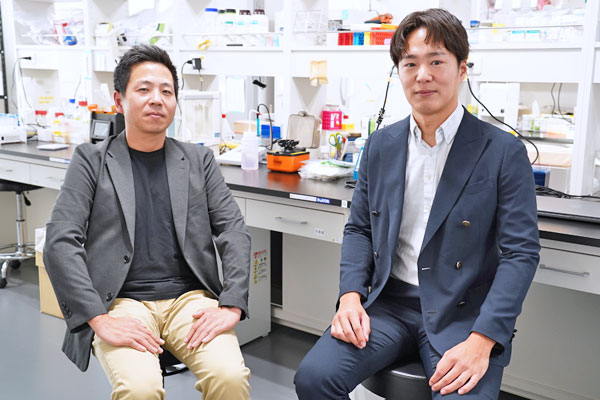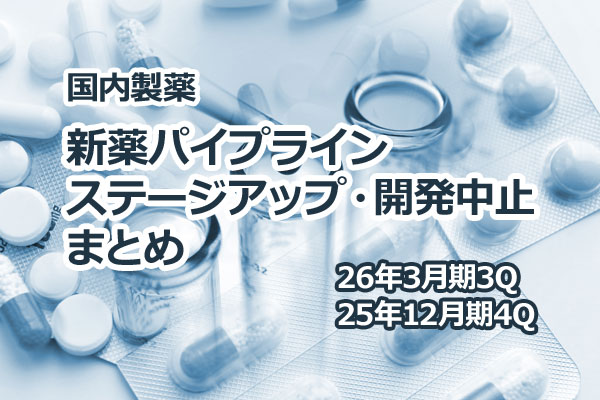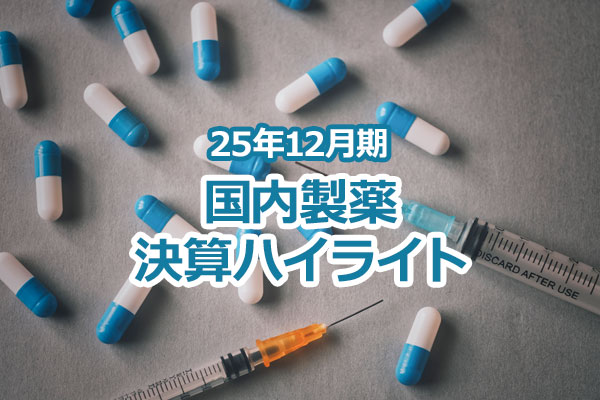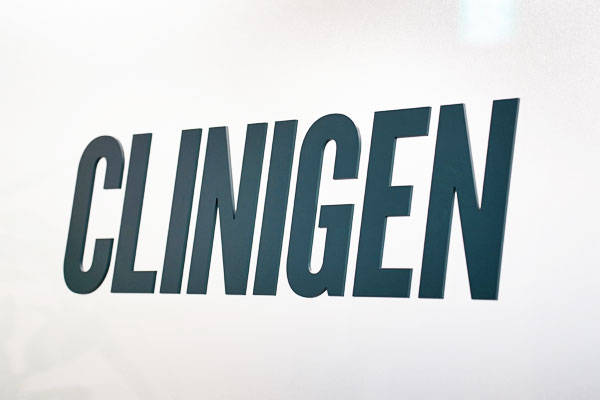
英国に本社を置く医薬品企業クリニジェンが、日本事業の拡大に動いています。日本では現在、海外の中小製薬企業と提携して国内で承認前の医薬品を製造販売する事業を中心に展開していますが、今後は毎年3件程度、新たな提携を結び、取り扱い製品を増やしていく考え。ヴァルン・セティJAPAC(日本・アジア太平洋地域)シニアバイスプレジデントと日本法人のエドワード・ライト社長は「今後2~3年で日本の売り上げを2倍にしたい」と話しており、MRやMSLを中心に人員も増やす方針です。
「人乳由来母乳強化物質」26年初頭発売へ
――クリニジェンがグローバルで展開しているビジネスについて教えてください。
セティJAPACシニアバイスプレジデント:クリニジェンは世界100カ国以上にネットワークを持つ企業です。かつては上場していましたが、2022年にプライベートエクイティの傘下に入り、非上場企業となりました。
私たちは自身を製薬企業・バイオテック企業に対する「サービスプロバイダー」と位置付けています。主なビジネスは、▽臨床試験に使う治験薬や対照薬の供給・調達支援する「臨床試験支援事業」▽製薬企業との提携を通じて承認前の医薬品の製造販売を手掛ける「医薬品製造販売事業」▽規制対応、ファーマコビジランス、医療情報サービスなどの「ライフサイクル管理事業」――で、これらを一気通貫で製薬企業やバイオテック企業に提供しています。
非上場企業なので具体的な数字は明らかにできませんが、グローバルでは5億ドル(約740億円)以上の売り上げがあります。そのうちのおよそ3割がJAPACで、さらにその3割が日本です。
日本はこれから注力していくマーケットの1つであり、厚く投資をしていく方針です。最近、人員も増やしていますし、今後も増員していきます。

クリニジェンのヴァルン・セティJAPACシニアバイスプレジデント
――日本国内ではどのような事業を行っていますか。
エドワード・ライト日本法人社長:日本では2013年にリンク・ファーマシューティカルズとして事業を開始し、その後、買収などを経て現在に至ります。私が日本法人社長に就任したのは昨年9月です。与えられたミッションは組織の再編と成長の加速。組織は現在、35人まで拡大しており、今後1年でさらに10人ほど増やしたいと考えています。
クリニジェン日本法人は、海外の中小のファーマやバイオテックに対して、日本での製品上市、日本への市場参入をサポートするビジネスを行っており、現在の主要なポートフォリオは4つのパートナーシップで構成されています。
1つ目は、2021年に世界に先駆けて日本で承認を取得したムコ多糖症II型治療薬「ヒュンタラーゼ」。韓国のGCバイオファーマと提携し、臨床開発から申請、承認、マーケティングまで行っています。きわめて希少な疾患で、日本でのユーザーは40人ほどです。
2つ目は、てんかん重積状態に対する治療薬「ブコラム」。スペインのニューラックスファーマがパートナーで、今年10月1日に武田薬品工業から日本での製造販売承認を承継する予定です(注:武田薬品は2020年10月にブコラムをニューラックスファーマに譲渡したが、日本では譲渡後も武田薬品が製造販売を行ってきた)。
3つ目のパートナーは英国のエッセンシャルファーマで、今年2月に韓国と日本での製造販売について提携しました。日本ではレーザー術後眼圧上昇防止薬「アイオピジン」と持効性抗精神病薬「ハロマンス」の2製品を年内に導入する予定です。
4つ目は米プロラクタ・バイオサイエンスとの提携です。日本のパートナーとして「人乳由来母乳強化物質」と呼ぶ製品を24年7月に申請しており、25年末の承認、26年初頭の発売を期待しています。これは、ドナーの母乳から抽出・加工される製品で、超低出生体重児らの成長をサポートします。日本では毎年、出生体重が1500グラムに満たない子どもが4000~5000人生まれています。プロラクタとの提携は私たちにとっても最も大きなもので、この製品の発売に向けて営業担当者を増やしていこうと思っています。

クリニジェン日本法人のエドワード・ライト社長
――これから日本事業をどのように成長させていきますか。
ライト氏:これから2~3年で日本の売り上げを2倍にしたいと考えています。既存製品の販売拡大に加え、新たな製品を追加していきたい。1年に新たに3つの契約を取り付けることができれば、というのが現在の私の展望です。
さらに、日本企業の海外進出を支援したいという気持ちも強く持っています。すでに実績もあり、塩野義製薬とは抗菌薬セフィデロコルのオーストラリアとニュージーランドへの展開で提携しています。
セティ氏:日本の大手製薬企業はすでにグローバル展開のルートを持っていますが、そうでない企業にもアジアやオセアニアへのルートを提供したい。クリニジェンはアフリカにもかなりのフットプリントがあり、アフリカも販売先となり得る。臨床からコマーシャルまでサポートできるので、大きな可能性を感じています。
日本での売り上げを2~3年で2倍にしたいという話がありましたが、それはAPACも同じです。将来的に10億ドルのビジネスに成長させたいと考えています。
多くの海外中小ファーマが日本に関心
――日本への投資を強化し、事業拡大に動くのはなぜですか。
セティ氏:日本の医薬品市場は今でも世界3位であることを忘れてはいけません。たくさんの海外の中小ファーマが日本に関心を持っており、私たちはそれをビジネスの機会ととらえています。さらに、大手企業の中には成熟製品を他社に承継するところもあり、私たちがその受け皿になるというところにもチャンスがあります。
ライト氏:ヘルスケアという面で考えると日本は非常に大きな市場。人口もそうだし、経済規模もです。政策や価格の問題はありますが、私が15年という比較的長い期間、日本のこの業界で活動してきて感じるのは、日本の当局は業界に対してオープンな姿勢を持ち続けているということです。一定の政策の方向転換はあるものの、大きな目で見ると安定した制度、システムがあると考えています。
ただ、安定はしているものの単純ではく、非常に入り組んだ複雑なシステムです。だからこそ、日本の制度に対する専門性を持った人材を抱える私たちのような会社が大きなインパクトを作り出せると考えています。専門性があるから海外企業の日本参入をサポートできるし、それがビジネスチャンスでもあります。
――一方で、日本では複数の製品をチェプラファームに承継しています。なぜでしょうか。
セティ氏:私たちのビジネスモデルには脆弱性があります。私たちは海外のファーマやバイオテックにパートナーシップサービスを提供しますが、それが一定以上の成功を収めると、自分たちで日本法人をつくって直接事業展開したいという意思を持つ企業も出てきます。これは自然な流れであり、そうしたリスクは日本だけでなくどこの市場でもつきものです。それを補完し、弾力性のあるビジネスを展開するには、そうしたこと(他社への承継)も必要なことだと考えています。
ライト氏:私たちのポートフォリオが変化していくのは何ら不思議なことではありませんし、むしろ自然なことです。最初は参入リスクを軽減するために私たちと提携し、その後、自分たちでやろうという企業が出てくるのもまったく自然です。私たちとしてはポートフォリオの刷新を常に行っていくことが重要であり、そのための新しい機会を常に積極的に模索しています。
もちろん、今ある製品を手放すことで新しい製品を扱えるようになるという面もあります。ただ、今後は売り上げ拡大を目指す中で、売り上げの拡大やポートフォリオの変化とともにスタッフも採用して組織を拡大させていく方針です。
私たちのビジネスモデルは、大々的に展開するような製品を導入して一気に売り上げを拡大させるようなものではありません。だからこそ、アジリティを持って希少疾患などの医薬品を導入することができます。そうしたところに、ファーマのエコシステムにおける私たちの存在意義があると考えています。