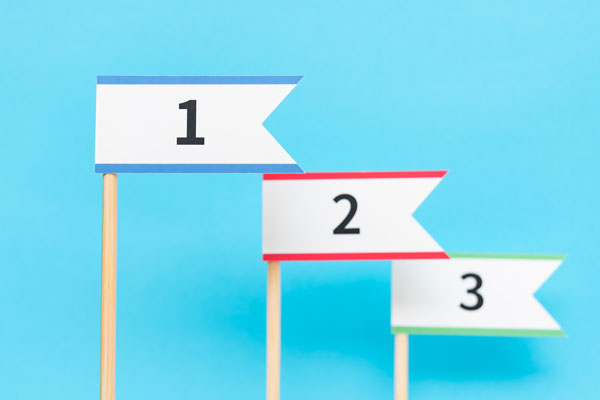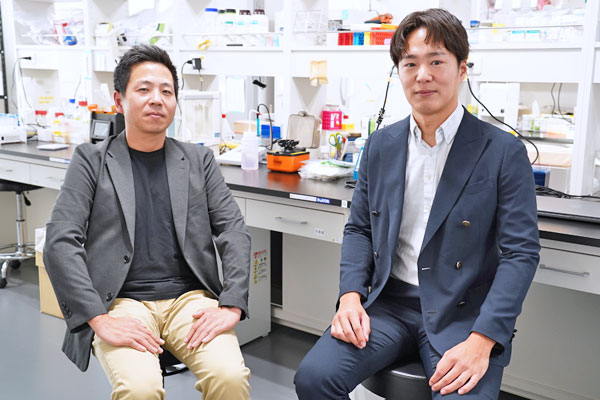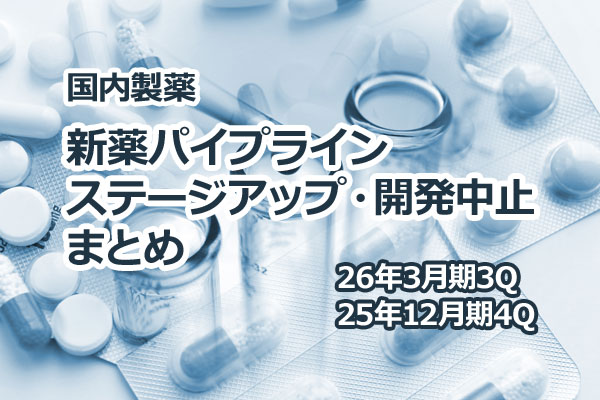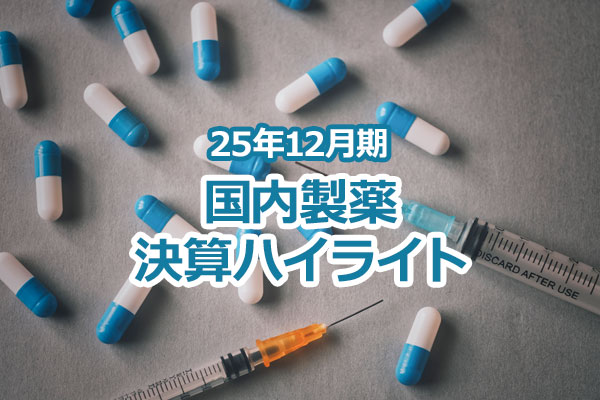トランスセラレート・バイオファーマのジャニス・チャンCEO
10月19~21日に東京都内で開かれた「DIA日本年会2025」の最終日、「臨床試験2035:研究の未来を変えるイノベーション」と題するセッションが行われ、臨床試験への参加を医療の選択肢の1つとして標準化する道を関係者が議論しました。このセッションに出席するため来日した非営利団体「トランスセラレート・バイオファーマ」のジャニス・チャンCEOに話を聞きました。
トランスセラレート・バイオファーマ…研究開発の非効率性をなくし、新薬をより早く患者に届けることができるよう、臨床開発の改善を目指して2012年に設立。トランスセラレートは「Transform(変革)」と「Accelerate(加速)」を組み合わせた造語。
大手製薬のR&Dヘッドが集まり2012年に設立
――トランスセラレートはどのような組織ですか。
ロッシュ、ファイザー、サノフィといった大手製薬企業のR&Dヘッド10人が集まって、2012年に設立されました。新薬開発コストが大幅に上昇し、世界各国の規制が非常に厳しくかつ複雑になる中で、研究開発に変革を起こして加速化させるのが目的でした。各社はサイエンスでは競合関係にありますが、オペレーションについては協業しています。
取り組みとしては、まずリスクベースモニタリングから着手しました。当時は各社が異なる手法を用いており、効率化の余地がありました。そこで、各社が自由に採用できるモデルアプローチを開発し、米FDA(食品医薬品局)からも関心を示しました。もう1つはGCP。治験実施施設向けのトレーニングについて、最低限の基準を共有し、相互認証を導入することで、企業側の業務効率化と負担軽減を図り、医療機関の負荷も下げることができました。
――世界各国の規制当局との関係は。
FDAや欧州の規制当局がわれわれの活動に興味を持っていますし、PMDA(医薬品医療機器開発機構)とも2014年以降、毎年会合を開くなど継続的に議論しています。各国の当局からは、複数のスポンサーが一丸となって共通のソリューションを組み立てていることが評価されています。
現在は世界18カ国の当局とやりとりしており、われわれが構築したソリューションについて早い段階で対話を持ち、意見を聞いています。たとえば、コロナ禍では多くの治験が影響を受ける中、プロトコルの逸脱回避のプロセスを構築し、多くのスポンサーに採用されました。
PMDAは非常にオープン
――PMDAとはどのような議論をしていますか。
PMDAとは毎年、定期的・継続的に話し合いの場を設けています。今後は治験のエコシステムプロジェクトが予定されており、jRCT(臨床研究等提出・公開システム)やICH-GCPの改訂などが注目されています。PMDAの治験エコシステムプロジェクトではIRB(治験審査委員会)の単一化や均一化が1つのトピックとなっており、われわれからどういったソリューションを提供できるか話し合っています。
10月21日のDIAセッションでは、PMDAから3つの注力すべき項目について説明がありました。▽臨床試験に革新をもたらす▽臨床試験のエコシステムの枠組みを作る▽AIを活用する―です。これらはまさに、われわれが注力しているところであり、今後の議論ではAI活用の事例も共有したいと考えています。
PMDAは非常にオープンで、われわれのような組織との意見交換を歓迎しています。われわれのソリューションなどに興味があり、海外の動向を学ぶことで日本でもイノベーションを確立したいという意識があります。PMDAの抱える課題は日本特有で他国にないものもあると思います。患者さんとのエンゲージメントについては、高齢化が進む中でDCTをいかに効果的に実現するかなど、日本の企業や業界団体、厚労省なども含めて真剣に検討されているように感じます。
――治験の効率化につながった取り組みの事例を教えてください。
あるメンバー企業では、プロトコルの共通テンプレートを活用することで設計にかかる作業時間を約20%削減できたと報告されています。データ共有を通じて、ある試験でコントロール群の組み入れ数を約50%削減したケースもあります。さらに、データ共有化により観察研究が不要になり、コスト削減につながった事例も報告されています。別の事例では、患者エンゲージメントツールの開発により、試験設計の初期段階で患者の意見を取り入れることが可能となり、登録率が20%以上改善した事例もあります。
共通テンプレートの利用は各社の判断に委ねられています。各社でどの程度のコスト削減につながったか確認はしていませんが、開発期間の短縮につながっているとの声は上がっています。われわれは、日常の治療を統合し、リアルワールドデータを常に入手できる形の治験を目指しており、そうした取り組みが治験期間の短縮につながると考えています。
現在、メンバーは20社に増えており、過去の治験に関するデータをシェアし、法的にしっかりとした枠組みを構築することで、多くの効率化を達成しています。プラセボ群の組み入れが減ったり、観察研究の必要性が下がったりした実績もあります。
DCT(分散型治験)については、成功例や上手くいかなかったケースをメンバー企業が共有しています。患者さんのエンゲージメントのために開発しているツールも、組み入れ期間の短縮や逸脱回避につながっています。
より多くの患者の参加を可能に
――日本は欧米に比べてDCTの普及が遅れていると言われます。
欧州の国々も同じような課題を抱えています。サイト側としては、大きな研究機関や大学病院は別ですが、依然として紙ベースであることも普及を遅らせている要素かもしれません。患者さんがリモートではなく対面を求める、高齢者はテクノロジーを使うことにハードルがある、といった理由も考えられます。米国立がん研究所のように、日本でもDCTに使える技術をしっかりサポートする体制が必要でしょう。
――患者エンゲージメントへの取り組みは。
臨床開発をさらに近代化する取り組みの一環として、患者さんに早い段階から関わってもらい、プロトコルの設計などに生かしています。われわれは、企業側が治験の早期段階で患者さんの声を直接聞けるようサポートするツールなどを提供しています。それにより、治験の期間中にフィードバックを常に入手できる環境を整えています。
――治験の将来についてどのようなビジョンを描いていますか。
治験を通常の定期的な治療と統合していくことを掲げています。現在、治験に参加できる患者さんは非常に限られており、より多くの参加を可能にするにはどのようなツールが必要か検討しています。大都市に住んでいたり大病院が近くにあったりするケースだけでなく、地方在住や社会経済的に困難な状況であっても参加できるようにしていきたい。そのためのソリューションを今後も開発するとともに、データの相互運用性やDCTといったさまざまな取り組みによって、世界中で治験をさらに効率的に運用できるようにと考えています。