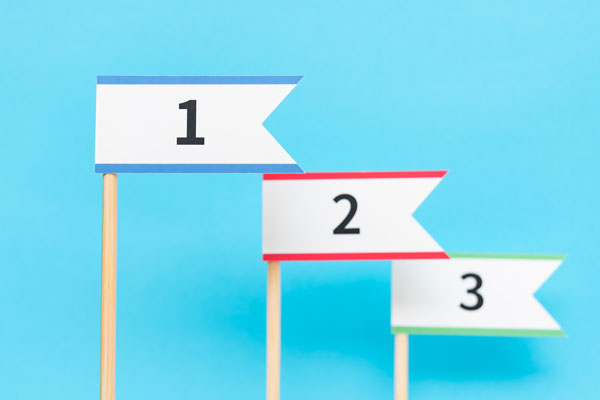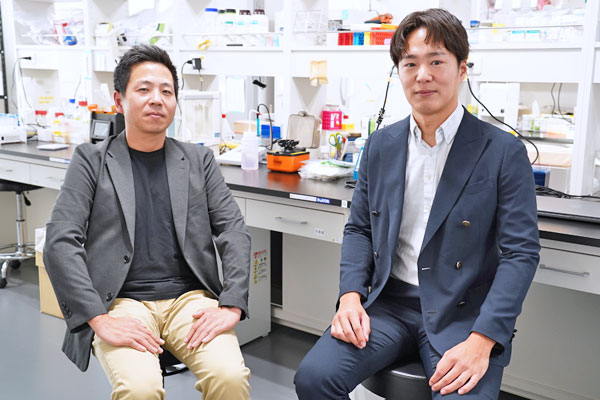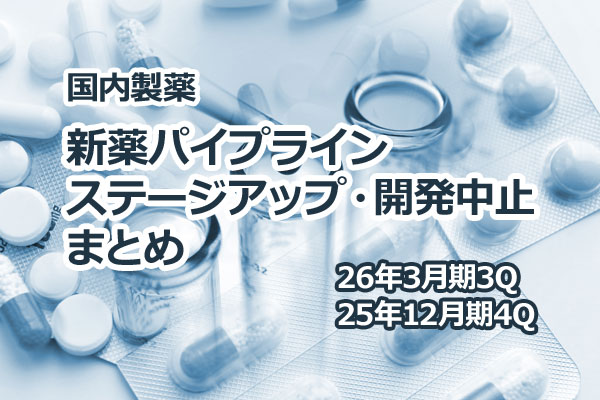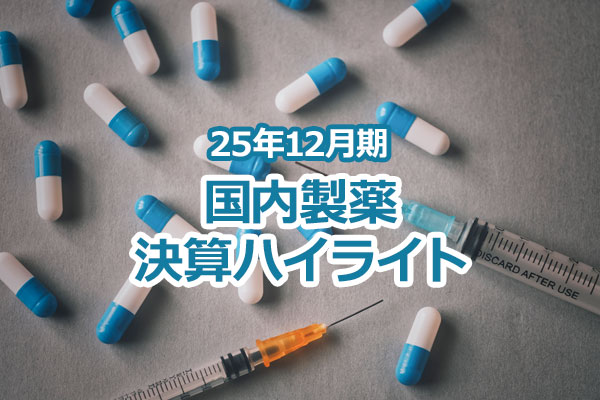神奈川県小田原市の小田急小田原線・富水駅から歩くこと約20分。市内を南北に貫流する酒匂川のすぐそばに、日本新薬の小田原総合製剤工場があります。
核酸原薬精製棟、26年度実製造開始へ
同工場は1964年に設立し、今年で61年。5万4215平方メートルの敷地で固形剤を中心に約60品目を生産しています。235人が働いており(2025年8月時点)、このうち生産に携わるのは半数弱。かつては本社を構える京都市にも医薬品工場がありましたが、2001年に小田原に集約されました。
小田原総合製剤工場で主に生産を担うのは、01年に建設された一般固形製剤棟と、17年に建った高生理活性固形製剤棟。設立当時に製造棟として建てられた1号棟は現在、QC/QA機能を持つ事務棟として活用され、注射剤の検査包装も行っています。10年までは注射剤の製造も行っていましたが、施設の老朽化によって検査包装のみに切り替えたといいます。
同社の主力品は、20年に国産初の核酸医薬として承認されたデュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬「ビルテプソ」(一般名・ビルトラルセン)。小田原工場では現在、同薬の製造工程の一部を内製化するため、24年に完成した核酸原薬精製棟の立ち上げ準備を進めています。
「核酸の製造は、原料製造から原薬合成、原薬精製、製剤・包装まで、全体でおよそ2年の時間を要します」と話すのは、同工場核酸製造技術部の藤木幹世部長。「現在は各プロセスを外部に委託していますが、安定供給につなげるべく、特に工程が複雑な原薬精製について、セカンドサイトとして内製化に取り組むことを決めました」。根本には「自分たちの製品は自分たちで作りたいという強い思い」があったと言います。
核酸医薬の原薬の精製工程では、合成された粗体品を入荷後、複数の分離・反応工程を通じて不純物を除去し、目的とする核酸を含む溶液を取り出します。その後、凍結乾燥、充填・包装などのステップを経て、精製工程が完了します。

核酸原薬精製棟の内部。【左上】移動相タンク(日本新薬提供)【右上】不純物除去に使うクロマトシステム(同)【左下】凍結乾燥機(同)【右下】オフィスエリア
現在は、26年度の実製造開始に向けて手順書作成などを行っている最中。イオン交換に使うカラムにはいくつも書き込みがされており、樹脂の詰め方などについて検討を重ねている様子もうかがえました。藤木さんは「核酸製造に向けて新たに必要な国家資格もたくさんあり、まずはどんな資格が必要なのか調べるところから始まりました。メンバーに手分けして資格取得をしてもらいながら準備を進めています」と言い、山口徹工場長も「これまで60年近く、ほぼ固形製剤だけを扱ってきたこともあり、非常に難しいスタートでした」と振り返ります。
BCPに力
小田原総合製剤工場は酒匂川に面し、富士山からも直線距離で40キロメートルという立地。地震や浸水、噴火を想定したBCP(事業継続計画)に力を入れています。
核酸原薬精製棟には特に厳重な対策を施しています。特徴的なのは防爆エリア。溶媒として大量のアセトニトリルを使用するためで、オフィスエリアとは区別しています。1階には3種の消火設備(泡・ガス・水による消火設備)を備え、発生場所に応じて使い分ける想定です。

【左上】核酸原薬精製棟の外観。浸水を防ぐために高床式となっている【右上】核酸棟の脇にある廃液を貯める場所も、浸水対策として高い外壁を設置している【下段】核酸棟の消火設備(泡・ガス・水の3種類)
取材では、「これまで固形製剤ひと筋だった」という藤木さんに、一般固形製剤棟も案内してもらいました。ここでは、従業員は朝7時半から19時の間で時差勤務を行っており、工程によっては夜間も自動で機器を動かしているといいます。

一般固形製剤棟の内部。製造実行システム(MES)を導入している【左上】造粒・乾燥・混合エリア【右上】打錠機【左下】外観検査を行う部屋。取材時は準備中で、検査は夜間に行われる【右下】洗浄中の包装ライン
一方、肺動脈性肺高血圧症などの治療薬「ウプトラビ」(セレキシパグ)などを製造する高生理活性固形製剤棟は、商業スケールの封じ込め仕様を備える国内最大級の流動層造粒乾燥機や、洗浄・乾燥を自動化した高速打錠機を備えます。日本新薬は現在、一般固形製剤棟で受託製造も行っていますが、今後は高生理活性固形製剤棟でも受託を行っていきたいとしています。

高生理活性固形製剤棟(写真はいずれも日本新薬提供)。【左上】外観【右上】流動層造粒乾燥機【左下】高速打錠機【右下】アイソレーター
工場全体で生産記録のデータ連携も進めています。現在はバラバラに存在する電子記録や手書きの記録書を連携・接続し、ダッシュボードで一覧できるようにすることで、品質の信頼性と作業効率の向上を図っていく考えです。工場では「コネクテッドファクトリー」と呼んでおり、1つの製造ラインからスモールスタートさせたところだといいます。
若手育成へ研修充実
核酸製造立ち上げに向けた組織再編も背景に、小田原総合製剤工場では近年、新卒採用も活発に行っており、若手向け研修の充実にも取り組んでいます。
同工場総務部の松永堅二部長は「GMP教育訓練などはもちろんしっかり行なっていますが、それ以外のキャリア別スキルやビジネススキルなどはカバーできていない部分もありました。そこで昨年から、若手向けに研修の機会を増やしています」と説明。25年度は新入社員の卒業論文発表会や核酸原薬精製棟の見学会、ロールモデルとなる部課長との対話などを行ったといいます。「安全衛生・環境(HSE)スキルの向上に向けた研修にも着手しましたし、今後はBCPの訓練もやっていく予定です」。

【左上】部課長(ロールモデル)との対話の様子。左は藤木さん(日本新薬提供)【右上】入社3年目の社員を対象に行ったローテーション研修。核酸原薬精製棟を見学中(同)【左下】労働安全衛生研修(同)【右下】食堂。交流を目的にe-sports大会が開かれることも
全社で推進するDXの取り組みも活発です。「(デジタルが)得意なメンバーが中心となり、機器を洗浄するロボットの導入や点検のアプリ化などにも自分たちで取り組んでいます。バイアル製剤の検査包装では、社員が開発したAIによる外観検査の構築も進めています」(松永さん)。